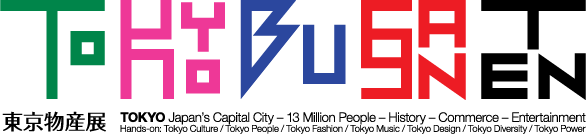時間を掛けて丁寧に作られる水出しコーヒーと温かみのある内装で、都内にありながら、静かでゆったりとした時間の流れるカフェ、クルミドコーヒー。つい長居したくなる心地よい空間が生まれたきっかけや、カフェという枠を超えた本を作る試み“クルミド出版”などについて、
オーナーの影山知明さんにお話を伺った。
カフェという場の可能性
元々影山さんの生家があった西国分寺でスタートしたクルミドコーヒー。当初は自らお店を経営するつもりはなかったが、出店を依頼した都内の人気カフェ「マメヒコ」の井川啓央さんに相談したところ、せっかくやるなら自分でやってみてはとアドバイスを受け、自身が運営することに。
「内装や最初のメニュー作りなど、全面的にマメヒコさんのお力をお借りしました。殻付きのクルミを自由に食べてもらえるようにしたのも、井川さんと話し合っているうちに生まれたアイデアです」
このお店の特色は、木の温もりを感じる内装や時間や手間をかけて淹れるコーヒーやケーキだけでなく、カフェの枠を超えた面白い試みにある。そのひとつが「クルミド出版」だ。
「カフェの可能性についていろいろ考えている時期があって、特に20世紀初頭のパリのカフェに興味があったんです。当時ピカソなど偉人たちがカフェに集まり、お互いに意見を交わしたりして才能を切磋琢磨していた。彼らの作品が生まれた背景を考えたときに、ある種の“場”というものが人を育てる装置になりうるんじゃないかと思ったんです。そんな時期に文章を書き溜めているお客さんに立て続けに会う機会があり、また、くるみ文具店といって文房具なども作っていたものですから、本を製本できるツテもあった。店内には本を置く本棚もある、これってもしかして出版社ができるんじゃないかと思っちゃったんです。それで本をつくることを決断しました。つまりお店に、カフェそのものだけでなく、さまざまな才能を育てる“場”としての可能性に賭けてみたくなったのです」

「東京らしい」カフェを目指して
東京という街での、これからのクルミドコーヒーの進むべき道を影山さんはこう話す。
「都市の魅力は、当たり前のことですが、たくさんの人がいることだと思うんです。色んな人がいて、関わり合うチャンスがある。でも、東京ってこれだけ人がいるのに、お互いがお互いを人として受け止め合っていない気がして。例えば電車に乗っているとき、たくさんの人がいるにもかかわらず、携帯電話や音楽を聴くことで誰もが人を受け止めるセンサーをシャットダウンしている。つまり、みんな自分のプライベートな行為を街の中に持ち出しているんです。実は東京の街には『パブリック』という関係性はほとんどなくて、人と人との関わり合いが起こりづらくなっている気がするんです。だからクルミドコーヒーは、訪れる人がお互いをちゃんと受け止め合えるセンサーを開けるような場にしたいと思ったんです。
5年間お店をやってみて、お互いが気持ちを開いて関わることで、さまざまな新しい可能性が生まれる瞬間をたくさん見てきました。大勢の人がいる東京だからこそ、可能性の芽は無数にあるはず。人と人のつながりが次々に生まれて、新しい試みに挑戦できる場。クルミドコーヒーという“場”は東京という街だからこそ、こういう姿になったのだと思います」